手術室は、麻酔科医、外科医、看護師、臨床工学技士など、複数の専門職が協働しながら、患者さんの命を守る現場です。なかでも、全身状態の管理を担う麻酔科医にとって、手術室看護師との連携はきわめて重要です。
しかし現場では、「この人とは安心して一緒に働けないな」と感じる看護師も、残念ながら一定数存在します。信頼を得られない原因は、必ずしも医学知識の不足ではなく、日々の姿勢や行動にあることが多いのです。
この記事では、麻酔科医の視点から「信頼されにくい行動」とその改善ポイントを紹介します。すべての麻酔科医に当てはまるわけではありませんが、手術室で信頼される看護師を目指す方にとって、自己を見直すきっかけになれば幸いです。
Contents
1.静脈ルート確保が極端に苦手、または判断力に欠ける
麻酔導入時に静脈ルートが確保できないと、麻酔薬や緊急薬の投与が不可能になり、患者の安全が著しく損なわれます(日本麻酔科学会, 2020年)。ルート確保は技術だけでなく、状況判断や報告力も大切です。
以下のような姿勢は信頼を損ないます:
- 何度も失敗した末に無言で麻酔科医に丸投げ
- 患者の血管の状態を確認せずにいきなり穿刺
- 難しそうな患者にも相談せず何度も挑戦を繰り返す
重要なのは「うまくいったか」ではなく「どう判断して、どう行動したか」。技術が未熟でも、「この患者は穿刺が難しそうなので相談したい」などと状況を適切に共有できる看護師は信頼されます。
2.出血量・尿量・ガーゼカウントなどの情報共有を怠る
出血量や尿量、ガーゼカウントのズレなどは、麻酔管理に直結する重要な情報です(厚生労働省, 2021年)。それらを「見ればわかるでしょ」と黙って処理するのは非常に危険です。
たとえば:
- 出血が急増しているのに麻酔科医が気づかず、輸液・昇圧剤の投与が遅れる
- ガーゼカウントが合わないことに気づかず、体内遺残や再開腹リスクが発生する
麻酔科医はモニターや術野の変化にも注意を向けているため、すべてをリアルタイムに把握することは困難です。だからこそ、「報告する」という基本行動がとても大切なのです。
3.術後覚醒期の患者対応が雑で危険
覚醒期は、麻酔科医が最も緊張する場面のひとつです。抜管前は、自発呼吸の再開や気道反射の有無など、ごく微細な変化を慎重に見極める必要があります。
このタイミングで:
- 看護師が離席して事務作業をする
- 患者に不用意に話しかける
- 気軽に身体に触れる
といった行動は、非常に危険です。わずかな刺激でも、嘔吐や気管支痙攣、興奮などを引き起こす可能性があるためです(日本集中治療医学会, 2022年)。
看護師の本来の役割は、「必要なときにすぐに対応できるようにそばで見守ること」。過剰な介入も無関心もNGです。麻酔科医が集中しているときには、何が求められているかを察し、必要に応じて静かに補助に回る姿勢が信頼につながります。
信頼される看護師に必要なのは「完璧さ」ではなく「姿勢」
麻酔科医が看護師に求めているのは、完璧な技術ではありません。それよりも:
- 「できないことを正確に把握し、適切に共有する力」
- 「常に患者の安全を最優先に考える姿勢」
こそが、信頼関係を築くために重要な資質です。
信頼は一朝一夕では築けませんが、「報告・観察・判断・補助」といった基本行動を丁寧に積み重ねることで、確実に信頼される看護師へと近づけます。
まとめ:信頼は“行動の積み重ね”で築かれる
この記事で紹介した内容は、すべての看護師に当てはまるわけではありません。しかし、自分の行動を振り返るきっかけになれば嬉しく思います。
「私、これやってたかも…」
「え、これってダメだったの?」
と思った方は、ぜひ今日から少しずつ行動を見直してみてください。必要なのは、特別なスキルではなく、「姿勢を変える勇気」だけです。
麻酔科医との信頼関係は、患者の安全を守るための土台であり、自分自身の業務をスムーズに進めるうえでも大きな武器になります。チーム医療の一員として、今よりもっと頼られる存在を目指していきましょう!
参考文献
- 日本麻酔科学会. 「周術期管理チーム医療ガイドライン」2020年版.
- 厚生労働省. 「医療事故調査制度に関する報告書」2021年度版.
- 日本集中治療医学会. 「気道管理と周術期のリスク管理」2022年版.
- Google. 「検索品質評価ガイドライン」2023年改訂版.
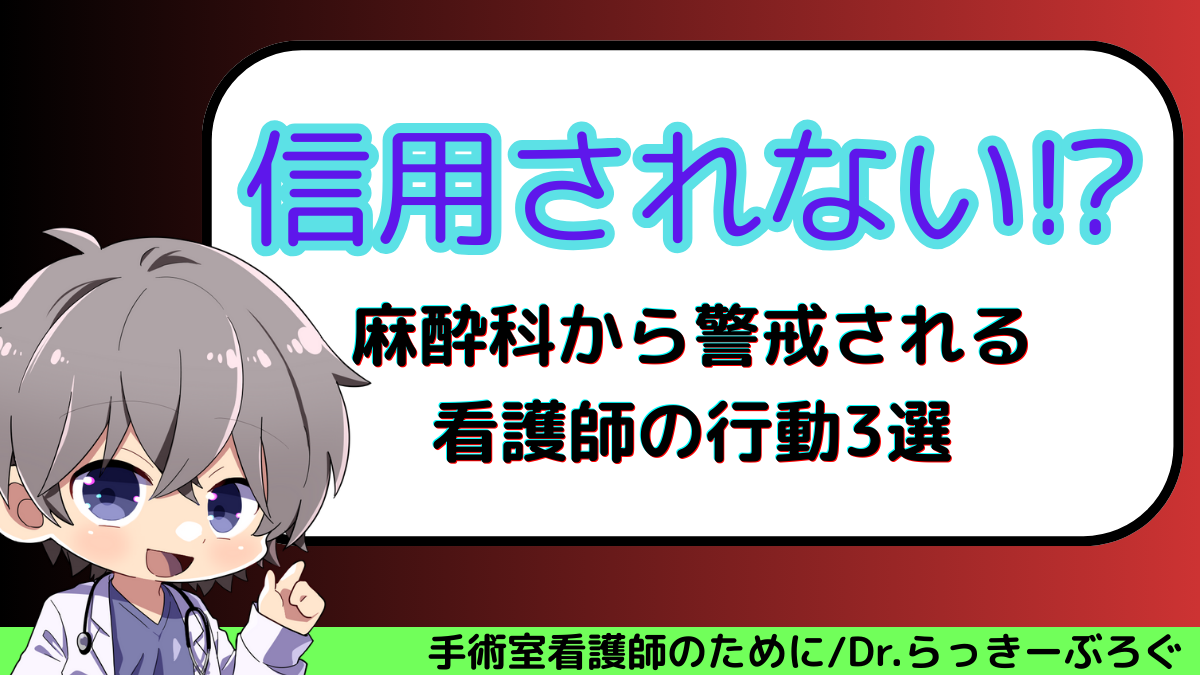
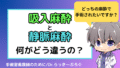
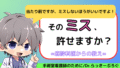
コメント