手術室での全身麻酔には、大きく分けて「吸入麻酔」と「静脈麻酔(TIVA)」の2つの方法があります。どちらも患者さんの意識を失わせ、痛みを感じさせないという目的は同じですが、それぞれに異なる特徴があり、手術内容や患者の状態に応じて使い分けられています。
この記事では、それぞれの麻酔法の違いや、現場での実際の選択基準について解説します。
Contents
吸入麻酔とは?メリットと活用場面
吸入麻酔は、セボフルランやデスフルランなどの麻酔薬を蒸気として吸入させる方法です。導入から維持までを吸入麻酔薬で一貫して管理できます。
メリットは以下の通りです:
- 個人差が少なく、麻酔深度の調整がしやすい
- 呼気濃度モニタリングが可能で覚醒の予測が立てやすい
小児や高齢者など、薬物代謝にばらつきがある患者でも安定した管理ができる点が利点です。
静脈麻酔(TIVA)とは?近年注目される理由
静脈麻酔は、プロポフォールやレミマゾラムなどを持続的に静脈から投与する方法です。導入が速やかで、覚醒も早いという特徴があり、近年は日帰り手術や美容外科などでも広く使われています。
主なメリット:
- 術後悪心・嘔吐(PONV)が少ない
- 吸入麻酔特有のにおいがなく、快適な導入が可能
特に若年女性や非喫煙者などPONVリスクの高い患者に好まれる傾向があります。
緩徐導入が必要かどうかが判断基準になることも
吸入麻酔は「緩徐導入」(意識があるまま徐々に吸わせる導入)に対応可能です。これは静脈路の確保が困難な小児や、全身麻酔に強い不安を抱える患者に対して非常に有効です。
一方で、成人で静脈ルート確保が容易であれば、静脈麻酔で十分なケースも多く、必ずしも吸入麻酔が必要とは限りません。
医療機関の設備や麻酔科医の好みも影響する
静脈麻酔の維持には、TCIポンプ(標的濃度制御型ポンプ)が必要です。これにより、血中濃度を一定に保った安定した麻酔管理が可能になります。
ただし、TCIポンプが未導入の施設もまだ存在しており、設備の有無が麻酔法選択に直結することがあります。
さらに、麻酔科医の経験や好みも影響要因の一つです。どちらにも長所・短所があるため、医師が自信を持って管理できる方法が選ばれる傾向にあります。
実際の使い分けの一例
以下のような場面で、使い分けがなされます:
- 長時間の開腹手術 → 吸入麻酔
- PONV回避が重要 → 静脈麻酔
- 静脈確保困難な小児 → 吸入麻酔(緩徐導入)
- 日帰りや美容外科手術 → 静脈麻酔
また、導入を静脈麻酔、維持を吸入麻酔という併用パターンもよく用いられます。
まとめ|吸入麻酔と静脈麻酔に優劣はない
吸入麻酔と静脈麻酔にはそれぞれ利点があり、どちらが「優れている」とは一概に言えません。
患者の状態、手術の種類、施設の設備、麻酔科医の経験など、多角的な視点から柔軟に判断されるべきです。
手術室看護師としても、各麻酔法の違いや選択理由を理解しておくことで、患者対応やチーム医療の質を高めることができます。
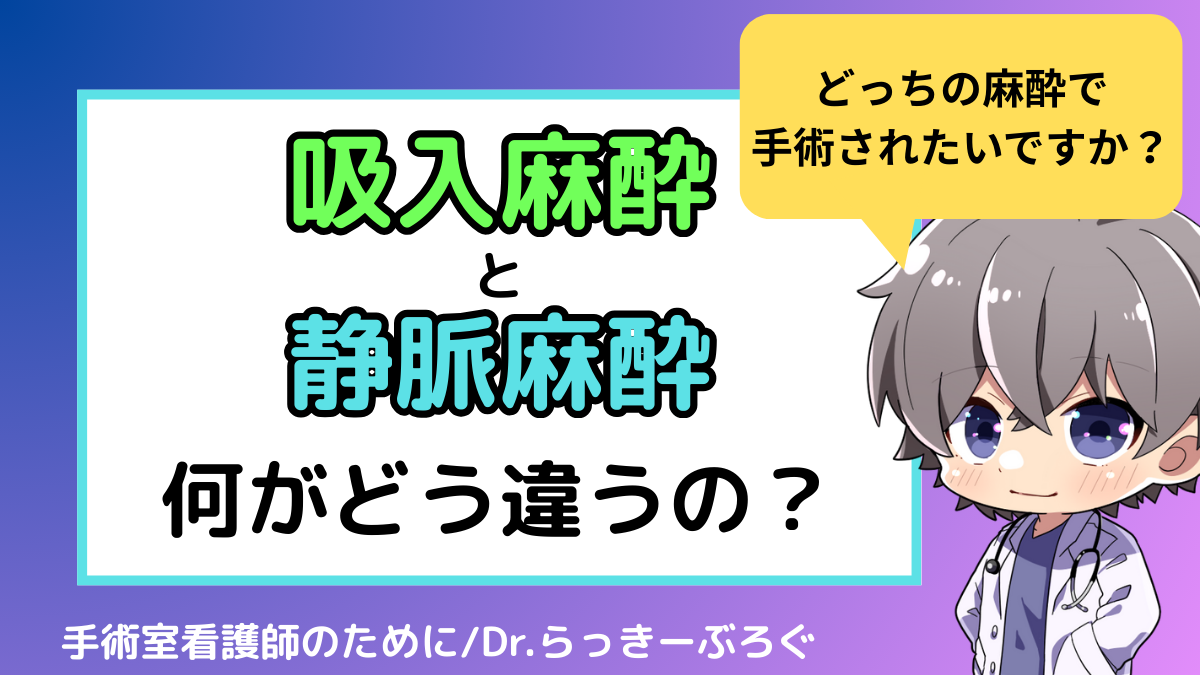
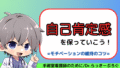
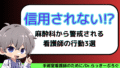
コメント